小ロット生産時の設備
Vol.23で、伸線工程ビジネスが独立しているので、少量の素材が安定的に入手可能である事を書きました。
ヘッダーやローリング工程では、他の国と同じ生産方法を取っている企業が多いので、差があまりつかないと思いますが、
その後の熱処理と表面処理工程では日本の強みが出ると感じています。
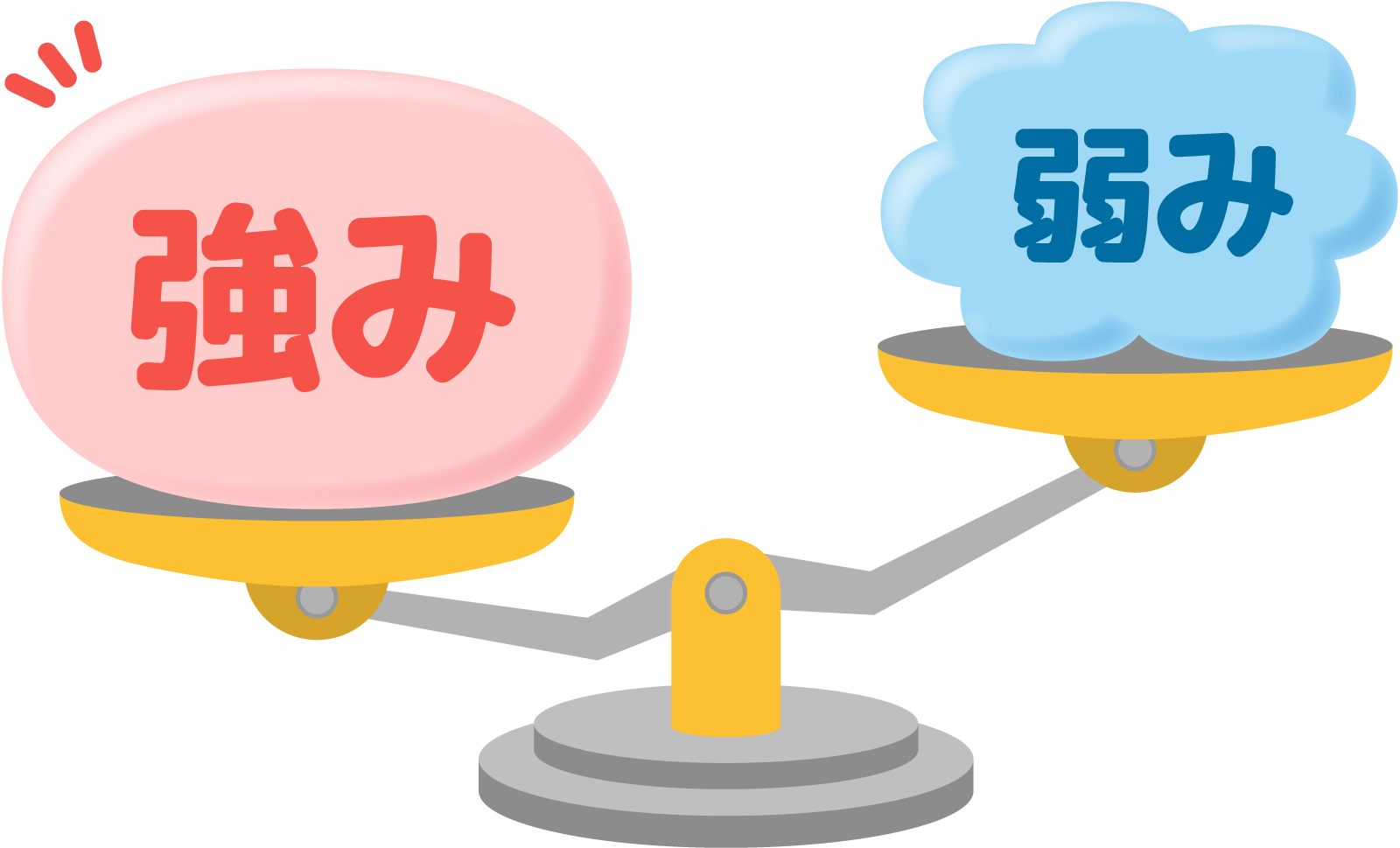
ねじ生産企業が自社内で熱処理設備を持っている場合は、極力同じサイズ、同じ素材の部品を処理したいので、
同じ部品を大量に生産するタイプのねじ工場に多いです。
これは、他の国でも同様なので、日本の強みの差別化がしにくく成ります。
・M2未満のミニチュアねじの熱処理設備
・M16、M20などの熱処理設備
・M72の熱処理設備
・浸炭材の熱処理
・調質材の熱処理
条件が違う熱処理を、それぞれの強みを持った熱処理企業を、日本国内で探すことが出来ます。
条件が違えば、設備の種類や大きさも違います。
日本のねじ製造サプライチェーンは、大抵の熱処理をカバーできます。
表面処理、特に電気めっきは電極にねじが触れる量まで投入する必要があるので、めっき部品の処理量でバレルの大きさを変える必要があります。
M1.4のねじと、M20のねじではめっき処理ラインの大きさが違います。
日本は、ミニチュアから大口径ねじまで処理可能な表面処理工場が揃っています。
さらに、小ロットでも大ロットでも処理可能です。
日本のねじ生産サプライチェーンの「強さ」は、こんな切り口でも体感できます。
[コラムニスト]
株式会社サイマコーポレーション
グループCEO & テクニカル・セールス
斎間 孝
